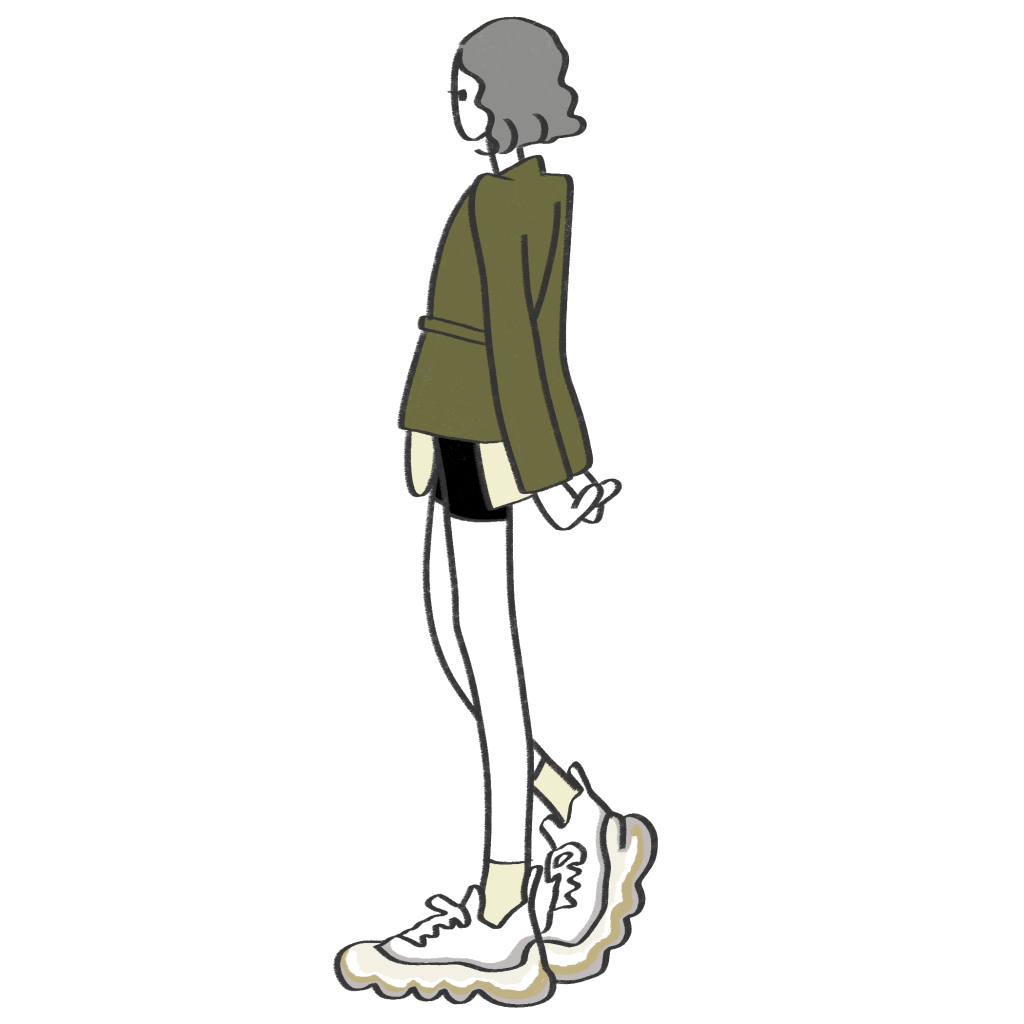私は美術館に行くことが好き。美術館で作品を見ることは、役者として演劇をおこなうことに似ている。
演劇というと、舞台の上で照明に照らされた役者が決められた台詞を言う様子を想像されるかもしれない。しかし演劇は、舞台や照明、あるいは台詞を必要とはしない。演劇であることの必要最低限の要素は、演劇を見る者の存在だ。
例えばあなたが、椅子に座って本を読んでいる。ここに演劇の要素は何もない。しかし、例えばここに、「椅子に座って本を読んでいるあなた」を見る人を、1人加える。この人は、何も話さない、ただ見ているだけの人であるが、あなたを見て「何を読んでいるのだろうか」「どんな人だろうか」「何を考えているのだろうか」といろいろなことを考え、読み取ろうとする。この人は、観客として機能している。
これだけではまだ演劇とは言えない。あなたは、観客に見られている自分を意識するのである。椅子に座る姿勢、ページを繰るタイミング、目線の動きを意識しだして、先ほどまで誰にも見られていなかった頃の自分とは随分様子が異なってくる。あなたの緊張の生まれや、感情の変化は、たとえ小さなものでも表情や身体に現れる。ここであなたは、役者として機能する。
すなわち、演劇に必要なのは、「見ること」と「見られていること」が同時に起こる空間である。そしてそこでは記号の発信と受信が行なわれる。記号とは、目に見えない感情や考えが表情や身体に現れたものである。例えば本を読んでいるあなたが緊張を感じたら、「緊張したな」と思わずとも、姿勢を変えたくなったり、呼吸が浅くなったりする。のどか乾いて、飲み物に手を伸ばしたりするかもしれない。一方の観客は、それらの記号を受信して、あなたの感情や背景を適切に解釈するための資源として使う。観客として記号を解釈することは、人間として生まれてからずっとやってきているコミュニケーションと同様なので、誰でもそれぞれできる。
ここで重要なことは、観客も記号を発信していることである。「お、その本は自分もすきだぞ!」とか「なにを考えているのかわからないなー」とか、考えていることは必ず身体に現れていて、それは椅子に座って本を読んでいるあなたにとてもよく伝わる。そしてこれに影響されたあなたの記号も、また違ったものに変わっていくのである。記号の伝達は、同時に双方向に行われるのである。
ここで、役者が見られていることを意識していない状況は、演劇とは言えない。例えば、町ゆく人を観客として見てみる。相手は見られていることを知らないし、こちらの存在に気づいてもいない。これは単なる人間観察で、ここに記号のやり取りは存在しない。また、録画された演劇を見ることも、演劇とは程遠い。
それでは、よい役者とは何だろう。私たちの身体は、自分が思っている以上に多くの記号を発信している。それらを制御することで適切な記号を発信できる人、観客の発信する記号を適切に受信できる人が、よい役者なのである。例えば「椅子に座って本を読む」という台本で、「本の中にある重要事項を見つけた」という演出(演技をどう見せるかという指導)があるとする。役者は、観客に見られているという緊張を制御して、本の中にある重要事項を見つけたという記号を発信しなければならない。それは、「目を見開いて、いきなり立ち上がる」という記号的な演技に留まる必要もない。「そのページを見つめながら、ゆっくり前のめりになる」「本を閉じて天を仰ぎ、椅子に身体を預ける姿勢になる」など、与えられた役の性格や背景、観客の発する記号によって、役者の動きは変わっていいものなのである。その柔軟さを持っていながら、なお演出に忠実な記号を発信できる人がよい役者なのである。
同じ台本、同じ演出でも、役者によってその表現は異なってくる。これは、それぞれの役者がこれまでの人生で経験してきたコミュニケーションが違うからだ。演技とは、台本にかかれた人物に100%なりきることでも、機械仕掛けの人形のように台詞を言うことでも、ありのままの自分を舞台に置くことでもない。自分と役の、間の存在を探すことである。だから、役者が違えば、演技が違うのは当然のことなのである。

美術館に行くと、私と作品と監視員だけという状況が時折生まれる。私がその展示室に入ることで空間が動き始め、私が監視員を意識することと監視員が私を見ることで、ここに演劇に似た構造が成立する。美術館にいるときの私は、展示作品を見ている側にもかかわらず、見られていることに意識的で、とても役者的。だから美術館はとても好き。