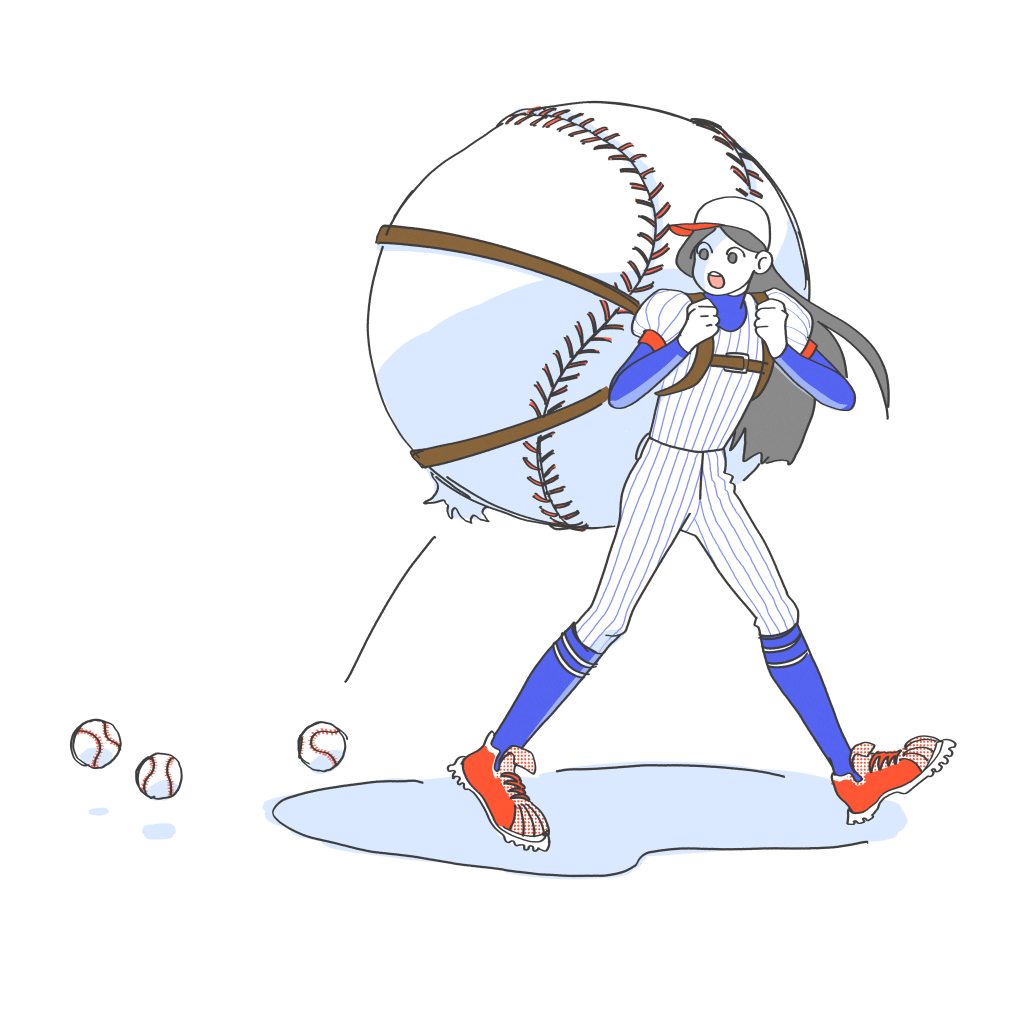エレベータで聞こえてくる男性2人の会話。
「この前、仕事終わりに、キンッキンに冷やしたグラスで、キンッキンに冷やしたビールを飲んで、もーめちゃくちゃ旨かったの」「へえ」「でもそれ、ノンアルコールビールだったの。普通に旨くてさあ、意外と気づかないのね!」
平和な話題だな、続けて耳を傾ける。
「それはいつ気づくんですか」「んん~いつだろうなあ…、でもね全然気づかなかったの。キンキンに冷やしたビール旨い!と思って。でもそれノンアルだったのよ!(2回目)」そしてエレベータを降りていく。
ああ会話が嚙み合わずに終わってしまった。おそらく片方の男性は「結局のところ冷えたビールならなんでも旨いよね」という共感が欲しくて話していて、もう片方の男性は話題を広げようとして厳密な質問をしたのだと思う。1度ではパッションが伝わらなかったから、2度も同じことを言っていた。その後は無事に伝わったのだろうか。何とも歯がゆい時間だった。なぜなら、話題を広げようとした後者の男性のやり方は、私がよくやってしまう会話の進め方と同じだったからだ。
生きていると恥は増えていく一方だ。少し前まで、私は会話が得意だと自負していた。具体的には「質問をすること」が得意だと思っていた。就活で使用した履歴書には特技に「質問すること」を書き、面接では自分語りよりも、質問をすることでいかに面接官に話してもらうか、という点に集中していた。友達との会話でも、自分は聞き上手だからと思い込み、いかに質問するかという姿勢を保っていた。ある話題について即時に質問できる集中力、また様々な分野に関する知識の豊かさが、会話術だと勘違いしていた。
しかし実際には、私の質問のおかげで空回りしていることの方が多い。これに気づいたのは最近のことだ。話題を広げようと質問をすることで、返って話の腰を折ってしまうのである。
例えば、友達との会話を想定してみる。「この前遊園地に行ったんだ」と会話が始まるとする。以前の私は、「おお、いつ行ったの?」あるいは「誰と行ったの?」と質問していただろう。相手は質問に答えてくれるので、会話は進んでいるように思えるが、そのやり方は尋問と等しい。もしかしたら相手は「遊園地で土砂降りが降って、そのおかげで空いていて乗り物にたくさん乗ることができた」と話したかったかもしれない。これは私の質問では到底たどり着かない内容なので、私の質問が話の腰を折っているということになる。相手は話したかったことが話せず、残念な終わり方となってしまう。
最近の私が思う最適な返事は、「いいね、どうだった?」である。共感とオープンクエスチョンだ。会話の正解は常に相手が持っている。相手が始めた話なので、内容は相手に委ねて問題ないのである。これで相手は気持ちよく話すことができる。
実際、私の相槌の言葉は相手にとってそれほど重要ではないことが多い。私は寝る前にその日の会話を思い出すことがあるが、ほとんど自分の発言しか覚えていない。これは相手も同じだと思う。結局は、相手が話したい話を満足にできたかどうかが重要なのである。
これに加えて最近分かってきたことは、ある程度相手が話し終わったら、私も勝手に話し出していいということである。「私も土砂降りのときにキャンプに行ったんだけど、生きるのに精一杯で楽しかった」とか。
傾聴を続けてきた私にとって、自分から別の話題を提供することは、挑戦的な試みである。私の話のあと、相手の反応を見て不安になることもある。特に無言の時間が流れると、「あれ、今のつまらなかったかな」とか「会話泥棒したかな」とか考えてしまう。しかし少し待ってみると、相手は相手で別のことを考えていて、私の話を基にした別の話題が始まる。相手と私で、自己開示の量が丁度同じくらいだと、気持ちよく会話を続けられる。こういった会話のキャッチボールによって、ときにお互いが思いがけない話題へ辿り着くことがあり、とても面白い。
そういえば演劇をやっていた頃、「脳の半分は相手の言葉を聞きながら、もう半分は別のことを考えているのが自然だ」と習ったことを思い出す。相手のセリフを聞きながら、自分のセリフの準備をすると、自然な会話に近い表現ができるのだ。
これまでの私は脳のほとんどを「いかに質問するか」に費やしていたが、質問は重要ではないし、もう少し自分のことを考えてもいいし、相手も同じように別のことを考えている、と信じて待つことができるようになってきた。会話の技術は、相手を信じて身を委ねることなのかもしれない。